はじめに
私が電気制御に携わる様になったのは、学校を卒業し、初めて就職した先が、自動車の生産機械、ラインを製造している会社であって、その配属先が電気設計であったことから始まります。
当時は、現在のようにパソコンも普及しておらず、シーケンス制御回路は、複数の電磁弁やモーターをON、OFFさせるのには、多数のリレーとタイマーを使用し回路を組んで構成し、そのシーケンスにより自動機械装置、機器を動かすという、装置の規模になるとかなり難易度のたかいものでした。各リレーやタイマーの接点のは、単線で圧着端子で各部品の端子に接続されますので、回路の設計にミスがあれば、まともな動作をしないわけで、回路の変更も配線変更作業が必要となります。現在使用しているPLC(プログラマブルロジックコントローラ)の様なモニター画面によるデバックも出来ませんので、難易度は非常に高く、社内テスト現場で一発で動くということはまずありませんが、その修正が多いとか、あまりにも時間がかかったりすると、大騒ぎとなります。
1970年代前半 電卓用4Bitマイクロプロセッサが出てから、そののち、1970年代に、8ビットのCPUが出始めました。
1974年4月 インテル 8080、モトローラ 6800、1976年7月 ザイログ Z80、1978年6月 インテル 8086
1978年6月 インテル 8086 16ビットCPU
これにより、ワンボードマイコンというトレーニングキットが販売され、各社の開発陣は勉強し、自社製のマイコンボードを開発、使用することのきっかけとなったと思います。
当初、多くのメーカーが、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を販売し始めたときにも重なります。(のちに早々、専用チップを起こしたとは思いますが、...基本、中身は同じです)
また、私が制御設計の立場から、パーソナルコンピューターの発売を見てきたのは
パソコン本体
1977年 アップル、タンディ・ラジオシャック、コモドール 、1979年 NEC PC8001、シャープMZ-80B
上記に使用されていたOSは、
BASICインタプリタをROMで搭載されたり、独自のDOS(様々な独自OS)だったり、
1979年 N-BASIC、DISK-BASIC
1970年代 CPM(デジタルリサーチ社)
1982年 MS-DOS(マイクロソフト)
その他のOSも、MACも含めて若干あったかと思いますが...。
大中小企業は、CPUを使用し、これらのパソコンを使用して、各社独自開発したCPUボード(ワンボードマイコン)に、アセンブラ言語、マクロアセンブラ、FORTH、PL/M言語により制御基板、機器を開発していくことになった。
これら以外にも上記進化、変化に並行して、スイッチ、表示灯類、センサーなどの入力機器、またモーター、電磁弁他などのアクチュエーターなど、様々な分野での発展がありました。
私が、たずさわった時期だけでも驚くべき発展です。
概要
マイコンCPUの出現と普及
ちょうど入社したそのころ、NECから”TK-80”という型式のワンボードマイコンが発売され、会社が買ってくれたので、マシン語コード(アセンブラ言語のコンパイルレベル)をボード上のテンキーから”1”と”0”で入力し、プログラムを実行させて勉強させてもらいました。例としてひとつ挙げると、ボード上のテンキーからの入力したA番地の数値内容とB番地の数値内容を加算してC番地に入れるなるプログラムを機械語で入力し、このプログラムを実行させて、結果をボード上の7セグメントの4桁のLED表示で確認するというものでした。
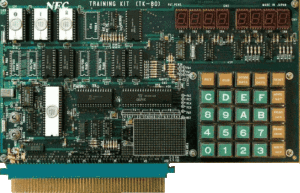

このボードに搭載されたCPUは、インテルの8080A(8ビットCPU)互換のNEC製マイクロプロセッサμPD8080Aというものでしたが、この後、1976年に米ザイログ社から発売されたZ80は、最も使用された8bitのCPUです。
この8bitのCPU教育キットが出回ったのをきっかけで、このボードで勉強した日本全国各社の開発社員達が独自のマイコンボードを開発、設計製作し、産業用の機械の制御に応用し始めたというところです。
![]()
このCPUとCPUを搭載したワンボードマイコンというトレーニングキットが販売されることにより、国内各社、自社製のマイコンボードを開発、使用することのきっかけとなった。
パソコン(パーソナルコンピュータ)の普及
また、時は同じくして、NEC(日本電気)からPC8000というパソコン(パーソナルコンピュータ)が発売されました。
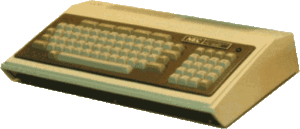
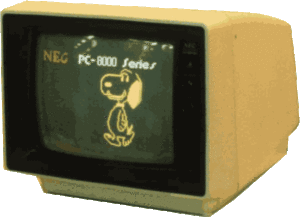

電源を入れるとROMBASIC(ロムベーシック)が立ち上がるというもので、接続されたCRTディスプレイを見ながら、アルファベットと数字キーでBASIC言語のプログラムを入力し、”RUN”とキーボードで入力すると打ち込んだプログラムが実行されるというものでした。当時は、作成したプログラムの記憶は、オーディオ端子から接続された端子からカセットテープの録音ボタンを押して、”1”と”0”を音で記憶するというものでした。当時はまだ、パーソナルコンピュータ用にはフロッピーディスク装置もない時代でした。ましてやハードディスク装置などはとんでもない話です。
海外製では、コモドールという会社が同じレベルのパソコンを日本で発売していた記憶があります。
※1977年 アップル、タンディ・ラジオシャック、コモドール 、1979年 NEC PC8001、シャープMZ-80B
まだまだ、数字とアルファベットの入力のみで、当初は日本語(かな、漢字)は扱うことは出来ませんでした。
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)の採用
当時、私のいた会社が採用していたものが、シャープのサテライトシリーズ、日立、積水化学、三菱電機、あと海外製品も営業に来られたかと記憶してます。
当時は、三菱電機は、ロジック回路入力方式、ステージ入力方式しかなかったため、ラダー回路と異なるため移行が難しい
日立は、ラダー入力方式であったが、ノイズに弱い印象(たまたま使った印象かも)
そこに、シャープが、ラダー入力方式でノイズに強いと売り込んできた、事実トラブルはなかった

しかしながら、全社全機種、いずれもプログラミングユニットというハンディ型のもので、プログラムを入力するもので、現在のようにノートパソコンで回路が表示されてデバッグも見やすいというものではなかった、確かわずか数行程度のプログラムが英数字で表示される程度であった。


そして、価格もまだ高く、リレーの置き換えには少し割高か、かなり割高というところ、ただし、メンテナンスとか総合的にみるとぎりぎり良いところとはいっても、初期の金額が高いと簡単に採用するというのは難しいところであった。
ということで、まだしばらくの間は、価格の面からリレーを使ったラダー回路で制御回路を作成し、制御されている装置が主流であった。

それから、急速に発展し、CPUの処理速度も上がり、PLCの価格も安価になると、複雑なリレー回路が主流に徐々にリレー回路からPLCに置き換わり はじめました。複雑なシーケンス回路の作成において言うと、実際に、リレーで回路作成とPLCで回路作成の比率が1978年に約”9対1”だったものが、約5年後には、約”3対7”くらいになったこ間隔を記憶しています。それでも当時はまだまだ価格も高いと、規模の大きい回路でなければ、メリットはありませんでした。
はじめました。複雑なシーケンス回路の作成において言うと、実際に、リレーで回路作成とPLCで回路作成の比率が1978年に約”9対1”だったものが、約5年後には、約”3対7”くらいになったこ間隔を記憶しています。それでも当時はまだまだ価格も高いと、規模の大きい回路でなければ、メリットはありませんでした。
その後、視覚的なプログラミングツールが、三菱電機から、”GPP”というプログラミングツールが発売され、これを機にPLCが三菱電機のシェアを格段に上げる時代がやってきました。当時は、このプログラミングツールのみで100万円ほどしましたが、ラダー回路の図を見ながら入力、デバッグすることができるので、リレー回路を行う設計経験者がプログラミングという言葉の難易度を下げてPLCを使い始めた結果、シーケンサーという名称で三菱電機のPLCが、大きくPLCを使用するきっかけを作りました。現在でも、シーケンサと言えばPLCというほどの知名度となっています。

そして、各社からPLCが発売されますが、....
 PLCも世の中に多く使われる様になると価格も徐々に安価な方向に、またノートパソコンが劇的に安価になったころから、各社のPLCのプログラミングツールがノートパソコンで、さらに使いやすくなりました。
PLCも世の中に多く使われる様になると価格も徐々に安価な方向に、またノートパソコンが劇的に安価になったころから、各社のPLCのプログラミングツールがノートパソコンで、さらに使いやすくなりました。
そして、現在では、リレーが4、5個レベル程度のボリュウムの回路でさえ、小型のPLCで価格的にも置き換えのメリットが出てきているのです。
操作盤も、入力押ボタンであったものが、タッチパネルで、状態表示灯に表示灯だったものが、画像表示でより分かりやすく表示ということで、タッチパネル表示器というものが、発売されPLCと同じように低価格となって、ひろまってきています。

また、センサーについても機械的なものはほとんど姿を消し、光電式、その他の非接触のものが当たり前の時代となっています。
生産ラインを自動制御する、制御の歴史
では制御の実際について下記に具体例を挙げてみます。
その流れは下記の様になりますが、...
押しボタンやリミットスイッチを入力とし、
![]()
![]()
![]()
![]()


※押しボタンはタッチパネル表示器などでも置き換えられています。
⇩
シーケンス回路の方法は、主に下記の方法1~4があります。
または
または
または
⇩
ソレノイドバルブやモーターのアンプを起動させることにより、

![]()
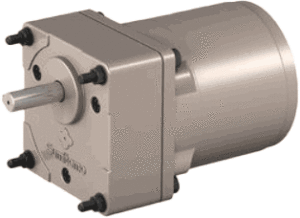
![]()
![]()

出力には状態を表示する表示器や表示灯もある
※表示器のところは、タッチパネル表示器に画像として表示されたりもしています。
エアーや油圧でシリンダーの直動をや、モーターの回転によりボールねじ、コンベアの搬送や
そのほかには、油圧リニアサーボ、温度調節器、...、電圧、電流調整器
指令から起動して単独に制御開始し、完了するもの
などなど、様々なものが現在でも使われています。
上位 作成例1~4の各シーケンスプログラムの作成例
作成例1: リレーとタイマーのみでシーケンス回路を作成
その制御が複雑であれば複雑なほど、多くのリレーやタイマーを使用し、動作シーケンス回路を組んで、
ひとつの制御盤で200~300個のリレー使用し回路を組むこともあり、部品点数が多ければ多いほど制御盤は大きくなり、故障率も高くなるためメンテナンスもその費用も大変な時代でした。


[ 動作シーケンス回路部分のみの使用部品 ]
MK 4P動作表示付き 5A 500万回 ¥3,690
MY 4P動作表示付き 3A 5000万回 ¥1,280
HH54 4P動作表示付き 3A 5000万回 ¥800
上用ソケット ¥800~1,000程度
[ 動作シーケンス回路部分のみの費用算定(設計費除く)例 ]
動作アクチュエーター ソレノイド16ケとして、動作シーケンス制御回路部のみ(仮にPLCのラダー回路部のみを比較するため)
・使用リレー数(MY4 or HH54 使用したとして、ソケット込み) 約64~80個 計¥144,000
・上記の配線工数 ¥50,000
合計 ¥194,000
※制御盤製作の上記を除く費用(制御盤箱、内臓のトランス、ブレーカー、電源回路、その他部品、配線費用は、別途¥350,000程度必要と推定)
[ 特徴 ]
作成例2: PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で、ラダー回路を作成




PLCの一般的プログラム作成機能であるラダー回路で動作シーケンスを作成
※他にもあるが、少数派
[ 動作シーケンス回路部分のみの費用算定(設計費除く)例 ]
動作アクチュエーター ソレノイド16ケとして、動作シーケンス制御回路部のみ(仮にPLCのラダー回路部のみを比較するため)
・I/O点数(例 入力42+8点、出力点数42点)
アクチュエーター16としても、入力には押釦、リミットセンサー、出力にはアクチュエーターON出力、動作表示灯+α などが必要
計¥110,000
・上記の配線工数 ¥10,000(取付治具含む)
合計 ¥120,000
※制御盤製作の上記を除く費用(制御盤箱、内臓のトランス、ブレーカー、電源回路、その他部品、配線費用は、別途¥350,000程度必要と推定)
[ 特徴 ]
作成例3: FAパソコン(ファクトリーコンピューター)に各言語で制御プログラムを作成

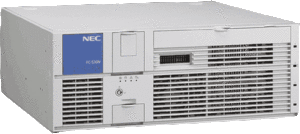

アセンブラ、VB、VC、C、C++、C#、JAVAなどで、動作シーケンス、上位との通信を含めて作成
[ 動作シーケンス回路部分のみの費用算定(設計費除く)例 ]
動作アクチュエーター ソレノイド16ケとして、動作シーケンス制御回路部のみ(仮にPLCのラダー回路部のみを比較するため)
・I/O点数(例 入力42+8点、出力点数42点)
アクチュエーター16としても、入力には押釦、リミットセンサー、出力にはアクチュエーターON出力、動作表示灯+α などが必要
計¥150,000~200,000
・上記の配線工数 ¥10,000(取付治具含む)
合計 ¥210,000
※制御盤製作の上記を除く費用(制御盤箱、内臓のトランス、ブレーカー、電源回路、その他部品、配線費用は、別途¥350,000程度必要と推定)
[ 特徴 ]
作成例4: マイコンボードに各言語で制御プログラムを作成
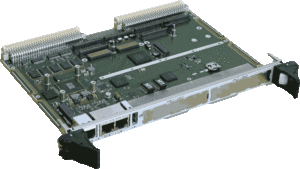
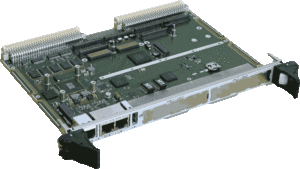

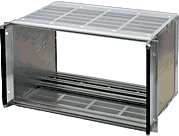
マクロアセンブラ、C、C++などで、動作シーケンス、上位との通信を含めて作成
[ 動作シーケンス回路部分のみの費用算定(設計費除く)例 ]
動作アクチュエーター ソレノイド16ケとして、動作シーケンス制御回路部のみ(仮にPLCのラダー回路部のみを比較するため)
・I/O点数(例 入力42+8点、出力点数42点)
アクチュエーター16としても、入力には押釦、リミットセンサー、出力にはアクチュエーターON出力、動作表示灯+α などが必要
計¥200,000~250,000
・上記の配線工数 ¥10,000(取付治具含む)
合計 ¥210,000
※制御盤製作の上記を除く費用(制御盤箱、内臓のトランス、ブレーカー、電源回路、その他部品、配線費用は、別途¥350,000程度必要と推定)
[ 特徴 ]
最後に
つくづく、面白い時代に生まれたなあと思うと同時に近未来にもっと々 期待です。
そこで、今まで経験してきた内容を技術情報として出来る限り紹介させて頂こうと思います。何か不明な点などがございましたら、なんなりとお問い合わせ下さい。
以降、必要項目を随時修正・追加し、内容を充実させていきたいと思います。
